日経平均はバブル後最高値を更新し、アメリカのS&P500やナスダックも史上最高値圏。ビットコインも熱狂が再燃し、まさに世界的な「お祭り相場」が続いていますね。
NISAやiDeCoで投資を始めたばかりの方も、ご自身の資産が日に日に増えていくのを、嬉しい半面、少し怖い気持ちで見ているのではないでしょうか?
「これはバブルなんじゃないか?」
「いつか暴落が来そうで怖い…」
「でも、ここで売ったら、もっと上がるかもしれない…」
こんな風に、”利益確定のタイミング”に悩んでいる方は、実は非常に多いと思います。
今回の記事では、この「売り時がわからない問題」について、まずはオーソドックスな利益確定の考え方をご紹介し、その上で、自身の苦い失敗談をお話しします。この記事が、あなたの投資のヒントになれば幸いです。
まずは王道を知る。利益確定の基本ルール3つ
感情に任せて売買すると、大抵うまくいきません。「もっと上がるはずだ!」という欲望や、「これ以上下がらないでくれ!」という恐怖に、合理的な判断が負けてしまうからです。
そこで、多くの投資家が実践している「機械的なルール」をいくつかご紹介します。大切なのは、買う前に売るルールを決めておくことです。
ルール1:「2倍になったら半分売る」
これは、非常にシンプルで強力なルールです。
【たとえば…】
ある会社の株を10万円分買ったとします。その後、株価が好調に上がり、評価額が20万円になりました(2倍!)。
ここで、持っている株の半分(10万円分)を売却します。
【どうなる?】
手元に現金10万円が戻ってきますよね。これは、最初に投資した金額(元本)とまったく同じです。
つまり、この時点であなたの元本は全額回収され、残りの10万円分の株は、いわば「タダでもらった」ような状態になります。
これ以降、この株がどれだけ上がろうと、たとえ価値がゼロになろうと、あなたが損をすることはありません。精神的にものすごく楽な状態で、さらなる株価の上昇を狙える、というわけです。
ルール2:「20%上がったら、持分の20%を売る」
「2倍になるまで待てない」「もっとこまめに利益を確定したい」という方向けのルールです。
【たとえば…】
100万円で買った投資信託が、120万円(20%上昇)になったとします。
ここで、評価額120万円の20%にあたる24万円分を売却します。
その後、さらに株価が上がり、残りの評価額が20%上昇したら、またその20%を売る…というのを繰り返していきます。
この方法のメリットは、上昇トレンドに乗り続けながら、段階的に利益を確定できることです。急な下落が来ても、すでに一部は利益として確保しているので、精神的なダメージを和らげることができます。
※ご自身の資産状況&リスク許容度に応じてこの利益確定ラインは10%にしたり、30%にしたり調整します。
ルール3:投資信託の「リバランス」戦略(プロも実践!)
iDeCoや積立NISAで、複数の投資信託を組み合わせている方に特におすすめなのが、この「リバランス」という考え方です。
これは、プロの年金運用ファンドなども実践している本格的な手法ですが、やることはシンプルです。
【たとえるなら…「カレーの具材バランス調整」】
あなたは「お肉60%、野菜40%」という黄金比率のカレーを作ろうと決めました。
ところが、お肉が思ったより早く煮えてしまい、鍋の中が「お肉70%、野菜30%」というバランスになってしまいました。
あなたならどうしますか?
きっと、増えすぎたお肉を少し取り出して、足りない野菜を追加しますよね。
【投資に置き換えると…】
最初に「株式60%、債券40%」という資産配分(ポートフォリオ)を決めたとします。
1年後、株式市場が絶好調で、あなたの資産は「株式70%、債券30%」に変化していました。
このとき、値上がりした株式(お肉)を10%分売って利益を確定し、そのお金で相対的に割安になっている債券(野菜)を買い増すのです。
【実例】世界最大の投資家、日本の年金基金「GPIF」の戦略
このリバランスを、世界最大規模で実践しているのが、私たちの年金を運用しているGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)です。
GPIFは、国民から集めた年金保険料の一部を、将来の年金支払いのために運用している組織です。その運用資産額は200兆円を超え、世界中の投資家がその動向に注目しています。
そんなGPIFが、長期的な資産運用のために定めている基本ポートフォリオがこちらです。
- 国内債券:25%
- 外国債券:25%
- 国内株式:25%
- 外国株式:25%
ここにGPIFの基本ポートフォリオの円グラフ画像を挿入
国内外の債券と株式にきれいに1/4ずつ分散していますね。そしてGPIFは、この比率から大きく乖離しないように、定期的にリバランスを行っています。
例えば、2020年のコロナショックで世界的に株価が暴落したとき、GPIFの資産に占める株式の割合は目標の25%を大きく下回りました。そこでGPIFは、値下がりした株式を大量に買い、逆に相対的に価格が安定していた債券を売りました。
そして、その後の株価の急回復局面では、目標比率を超えて値上がりした株式を売り、債券を買い戻したのです。
まさに、「安く買って、高く売る」を、感情を一切挟まず、ルールに則って淡々と実行しているわけです。私たち個人投資家、特にiDeCoやつみたてNISAで長期的な資産形成を目指す会社員が、最も見習うべきお手本と言えるでしょう。
でも、現実は甘くない。初心者が陥りがちな3つのワナ
さて、ここまで教科書的なお話をしてきました。ルールを決めるのは大事です。しかし、現実はもっと複雑で、感情が判断を狂わせます。特に投資初心者が陥りがちなワナがいくつかあります。
私の経験も踏まえると、大きく分けて以下の3つが挙げられます。
1.「もっと」という欲望に飲み込まれる(利確が遅れるワナ)
株価が順調に上がると、「まだ上がるはずだ」「もっと利益を増やしたい」という気持ちが強くなります。天井は誰にも分かりませんから、欲をかきすぎると、せっかくの利益が減少したり、最悪の場合は含み損に転じたりすることもあります。特に大きな含み益が出ると、「いつか大暴落が来るのでは」という恐怖と、「まだ上がる」という欲望の間で板挟みになり、結局売り時を逃しがちです。
2.「怖い」という恐怖に支配される(利確が早すぎるワナ)
逆に、少し利益が出ただけで「せっかくの利益を失いたくない」「暴落が来るのが怖い」と感じ、すぐに売却してしまうケースです。特に、過去に損失を出した経験がある方や、含み損を経験した直後などは、この恐怖が強く働き、冷静な判断ができなくなります。結果として、その後に株価が大きく上昇する「大化け」を逃してしまうことになります。
3.根拠なき「回復への期待」で塩漬けしてしまう(損切りできないワナ)
買った株が値下がりしたとき、「これは一時的なものだ」「いずれ回復するだろう」と、明確な根拠もなく持ち続けてしまうことです。損切り(損失を確定させること)は精神的に非常に辛い行為ですが、損切りができずに株を「塩漬け」にしてしまうと、本来もっと成長する可能性のある他の投資機会を逃してしまいます。また、含み損が拡大し続けることで、日々の精神的な負担も大きくなります。
これらのワナに陥ると、結果として「買ったら下がる、売ったら上がる」という感覚に陥り、投資に対する自信を失い、混乱してしまいます。そして、せっかくの利益を大きく伸ばせない、という状況に陥りがちです。
これらのワナは、私自身も何度も経験し、大きな後悔をしてきました。
ここからは、私自身の恥ずかしい失敗談を4つ、正直にお話しします。
私の「早すぎ&遅すぎ」大失敗談
さて、ここまで教科書的なお話をしてきました。ルールを決めるのは大事です。しかし、現実はもっと複雑で、感情が判断を狂わせます。
ここからは、自身の恥ずかしい失敗談を4つ、正直にお話しします。
失敗談1:FPG(9418)〜早すぎた利確〜
コロナショックですべての株が暴落していたころ、FPGという会社の株を買いました。業績はコロナ禍でおおきく落ち込むも、その後は回復基調にあり株価も順調に上昇。あっという間に含み益が30%を超えました。
当時はこう思いました。「すごい!30%も利益が出たぞ!欲をかかずに、ここで一度利益を確定するのが賢明な投資家だ!」
そして、喜び勇んで売却ボタンをクリック。
その後の株価は…売った価格から、さらに約5倍に大化けしました。
5倍株を、ほんの入り口で手放してしまったのです。「ルール通り」のつもりが、とんでもない機会損失を生んでしまいました。
失敗談2:電源開発(J-POWER)〜早すぎた利確〜
次に、電源開発という電力会社の株です。これは手堅い大型株で、大きな値上がりは期待できないと思っていました。
ところが、これも順調に上昇し、30%ほどの利益が出ました。
そして考えます。「この安定株で30%も利益が出れば十分すぎる。ごちそうさまでした!」
そして売却。
その後、ご存じの通り石炭市況の高騰による権益投資拡大(電源開発は石炭の権益投資もしている)、また最近は海外電力事業の好調で株価は売った価格の2倍程度にまで上昇しました。
また購入当時は高配当株としても有名で、配当利回りは5%超(当時)。その後も増配基調にあることも考えると、株価以上の逸失利益を出してしまっています。
手堅いと思っていた株でも、市場の風向きが変われば、大きな上昇気流に乗ることがある。それを身をもって知りました。
失敗談3:日本郵船〜恐怖からの微益撤退〜
これが一番、精神的にこたえた取引です。
コロナショックで株価が暴落したとき、「これはチャンスだ!」と思い、海運大手の日本郵船の株を買いました。しかし、その後も株価は下がり続け、一時は大きな含み損を抱えることに。毎日、減っていく資産を見るのは本当に辛いものでした。
やがて市場が回復し、買値まで株価が戻り、ほんの少しだけプラスになりました。
その時の心境はこうです。
「助かった…!もうあんな怖い思いはしたくない。少しでもプラスのうちに、とにかく逃げよう!」
恐怖から解放されたい一心で、すぐに株を売却しました。
言うまでもありませんが、その後、海運バブルが到来し、日本郵船の株価は売った値段の10倍以上に駆け上がっていきました。
この失敗から学んだのは、「欲望」だけでなく「恐怖」もまた、正しい投資判断を狂わせるということです。
失敗談4:北海道電力〜遅すぎた利確、そしてその先へ〜
これは「早すぎた利確」とは逆のパターンです。
ロシア・ウクライナ戦争をきっかけにした燃料価格の高騰で、北海道電力は巨額の赤字に。無配に転落し、株価は歴史的な安値圏に沈んでいました。「さすがに売られすぎだろう」と、まさにその大底で株を買いました。
その後、ラピダスの半導体工場進出やAIデータセンター需要への期待から、株価は劇的に上昇。一時は買値の3倍以上になりました。含み益はどんどん膨らんでいきます。
思いました。「これはすごいことになるぞ!まだまだ上がるに違いない!」
しかし、その後、上昇の勢いは止まり、株価は下落に転じます。みるみるうちに含み益が減っていく。
「まずい、まずい…でもまた上がるはずだ…」
そうこうしているうちに、含み益はピーク時の半分以下に。これ以上の利益の目減りに耐えられなくなり、結局、わずかな利益(+30%程度)で売却してしまいました。
天井で売ることはできなくても、もっと早く売っていれば…。「もっと、もっと」という強欲が判断を鈍らせ、大きな利益を取り逃がしてしまった典型的な失敗です。
そして、この話にはまだ続きがあります(苦笑)。私が諦めて売却した直後、なんとそれが再びの底値だったのです。その後、北海道電力の株価はそこから再び2倍以上に急上昇していきました。
この痛恨の経験から、私ほど(おかげさまで)1億円以上の資産を持つ投資家であっても、相場の天井や底を正確に読み切ることなど、到底不可能だと痛感しました。相場は常に私たちの想像を超えて動く、ということを改めて思い知らされた失敗談です。
では、どうすればいいのか?
失敗談でお分かりいただけたように、利益確定に「唯一の正解」はありません。どんなルールを使っても、後から見れば「早すぎた」「遅すぎた」ということは必ず起こります。
では、私たちはどう考えればよいのでしょうか。
ここで、伝説の投資家ウォーレン・バフェットの師であるベンジャミン・グレアムの教えを、バフェットが引用したとされる言葉をご紹介します。(※厳密にはピーター・リンチの言葉として有名ですが、趣旨は同じです)
利益が出ている株を売り、損失が出ている株を持ち続けるのは、花を摘んで、雑草に水をやるようなものだ。
まさに、自分がやってしまったことです。
- FPGや電源開発、日本郵船 → 元気に育っている「花」を、もっと大きくなる前に摘んでしまった。
- 北海道電力 → 満開になった「花」を欲張って眺めているうちに、枯れ始めてしまった。
- (もし含み損の株を持ち続けていたら)→ 枯れかけている「雑草」に、「いつか花が咲くはずだ」と祈りながら水をやり続ける行為。
私たちが本当にやるべきことは、元気な「花」(=成長している優良資産)を育て続け、枯れた「雑草」(=成長が見込めない資産)は見切ることなのかもしれません。
結論
- 個別株投資の方へ:
なぜその株を買ったのか、という「投資の根っこ」を忘れないでください。「株価が上がったから売る」のではなく、「この会社の成長ストーリーが終わった」と判断したときに売るのが、本来の姿なのかもしれません。 - 投資信託やiDeCoで積立をしている会社員の方へ:
そもそも、あなたがやっているのは「市場のタイミングを計らない」長期的な資産形成です。日々の値動きに一喜一憂する必要は全くありません。
一番の戦略は、「何もしないこと」かもしれません。
年に一度、GPIFのように「リバランス」で資産の比率を整えるくらいで、あとは淡々と積み立てを続ける。これが、凡人が天才的なトレーダーに勝つための、最も確実な方法です。
「売り時がわからない」と悩むのは、あなたが真剣に資産と向き合っている証拠です。
しかし、完璧なタイミングで売ることは誰にもできません。それならば、大きな心で、自分の資産という「花」がどこまで育つのかを、じっくり見守ってみるのも一つの立派な戦略ではないでしょうか。
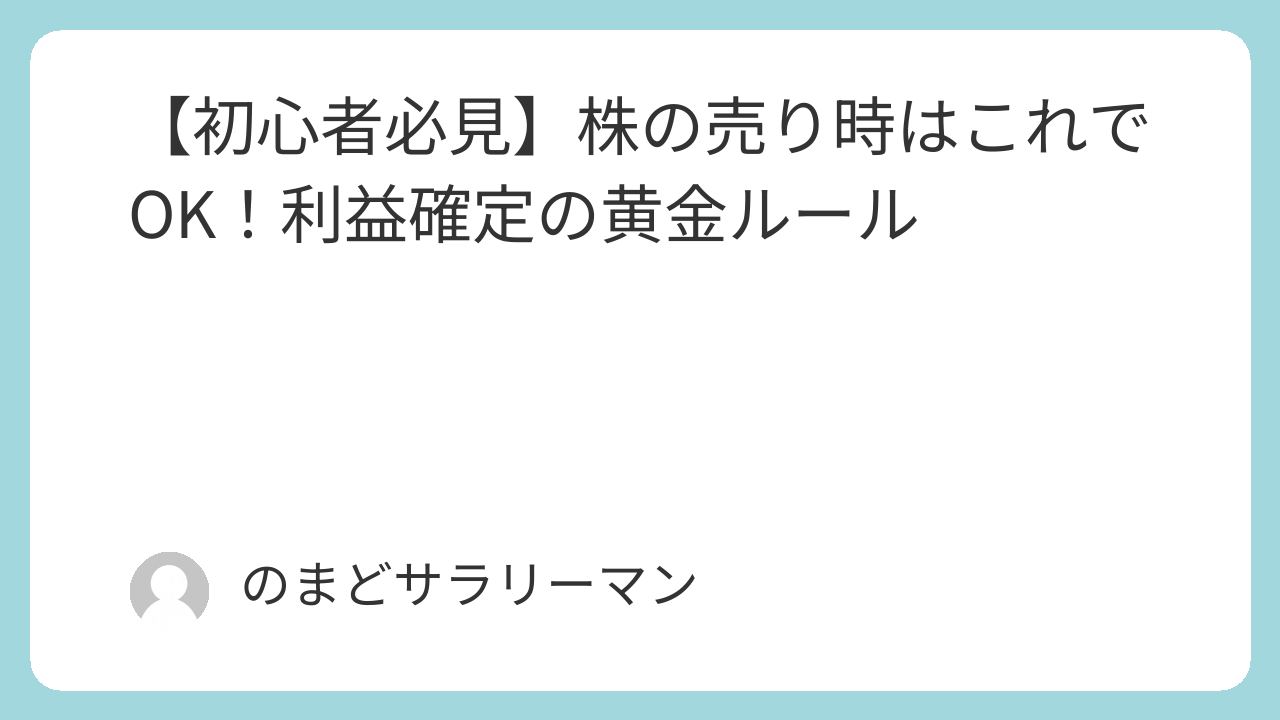
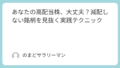
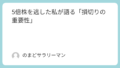
コメント