「配当利回り7%超え、さすが元国営企業。盤石だろう」
2020年ごろにさかのぼります。まだ投資初心者だったころの私がJT(日本たばこ産業)に投資した時の、甘すぎる見立てです。ご存知の通り、コロナショックにくわえ、喫煙人口の減少という逆風が吹き荒れる中、同社の株価は下落の一途をたどっていました。しかし、株価が下がることで、配当利回りは異常なほど魅力的な水準に達していたのです。
「この配当金をもらい続ければ、株価の下落はカバーできる」。そう信じ、時間分散しながら買い向かいました。
しかし、現実は非情でした。2021年2月、長年続いた連続増配神話は、あっけなく崩れ去ります。
JT(日本たばこ産業)、上場来初の「減配」を発表し、配当利回り7.1%⇒6.0%に! 2021年12月期から配当の方針を変更、前期比24円減の「1株あたり130円」に
出典: ダイヤモンド・オンライン 2021年2月9日 記事リンク
「初の減配」という衝撃で株価はさらに下落。私は含み損に耐えきれず、結局損切りを選択しました。
ここからが、この失敗談の重要な続きです。皮肉なことに、その後JTの業績は回復し、配当は増配基調に戻りました。株価も底を打ち、見事なV字回復を遂げたのです。
普通なら「あの時、売らなければ…」と後悔しそうですよね。しかし、私はこの損切りを一切後悔していません。 なぜなら、減配とは別に、海外での将来的な訴訟敗訴リスクという、財務諸表の数字だけでは測れない懸念を拭えなかったからです。そもそも最初から、私が許容できるリスクを超えた案件に手を出していたのです。(これは完全に私の考えであり、JT株を否定するものではありません。)
この痛恨の失敗は、二つのことを教えてくれました。一つは目先の数字の裏にある企業の本質を見抜くこと。そしてもう一つは、自分なりの投資哲学を持つことの重要性です。この記事では、その学びの核となった「減配リスクを炙り出す分析手法」を、具体的な企業の盛衰と共に、余すことなくお伝えします。
なぜ高利回りだけでは危険なのか?2つの事例が教える「見せかけの配当」の恐怖
私のJTでの失敗は、決して特殊な例ではありません。この罠の構造を理解するために、まず基本に立ち返りましょう。
そもそも、なぜ配当利回りが高くなるのでしょうか?主な理由は2つです。
- 増配したから(ポジティブ)
- 株価が下落したから(ネガティブ)
私たちが陥りがちなのは、後者の「ネガティブな高利回り」です。業績の悪化や将来性への不安から株価が売られ、結果的に利回りが高くなっているケースです。このような銘柄は、一見割安に見えるため「お買い得」と錯覚してしまいますが、実際には企業が稼ぐ力を失っており、いずれ配当を維持できなくなる可能性を秘めています。
この「見せかけの割安株」に飛びつくことこそが、バリュートラップの正体なのです。
そして、この「ネガティブな高利回り」がいかに恐ろしい結末を迎えるか、二つの事例が教えてくれます。
ケース1:日産自動車 (7201)
かつて高配当株のスター的存在だった日産。2018年頃には5%を超える配当利回りを誇り、それはまさに「株価の下落によって」もたらされた危険なシグナルでした。しかし多くの投資家は「さすがグローバル企業」とその数字の魅力に目を奪われます。その裏で事業の競争力が蝕まれていることに気づかずに…。結果はご存知の通り、業績の急降下とともに大幅減配、そして「無配」へと転落。株価も暴落しました。
ケース2:日本製鉄 (5401)
鉄鋼業界の巨人も、同じ罠を内包しています。鉄鋼業は典型的な景気敏感(シクリカル)業種。好景気の時は莫大な利益を上げて高い配当を出しますが、ひとたび不況になれば業績は急激に悪化し、配当はあっさり減配、時には無配となります。2020年には実際に無配に転落し、多くの配当狙いの投資家が涙をのみました。好景気の時の高い利回りだけを見て投資すると、不況の谷で手痛いしっぺ返しを食らうのです。
これらの事例が示すのは、「利益の裏付けがない、あるいは不安定な高配当は、砂上の楼閣に過ぎない」という厳然たる事実なのです。
【実践編】減配リスクを見抜く3つの鉄壁フィルター
では、どうすれば企業の「源泉」を見抜けるのか?私がJTと日産の失敗から編み出した、3つの鉄壁フィルターをご紹介します。
フィルター1:財務の要塞度をチェックせよ! 〜リーマンを生き抜いたオリックスの秘密〜
企業の体力、それは何と言っても財務の健全性です。
この重要性を教えてくれるのが、オリックス (8591) です。2008年のリーマンショック。世界中の金融機関が破綻の危機に瀕し、オリックスの株価も一時は9割引という壊滅的な打撃を受けました。当然、配当も大幅な減配を余儀なくされます。
しかし、オリックスは潰れませんでした。なぜか。それは、危機以前から築き上げていた強固な自己資本と、多様な収益源があったからです。金融危機という最悪の嵐を耐え抜き、事業を再建。そして今や、再び連続増配を続け、株主還元の優等生として返り咲いています。
チェックポイント:
- 自己資本比率: 40%以上あるか?(オリックスは苦しい時期も一定の資本を維持した)
- D/Eレシオ: 借金に頼りすぎていないか?
嵐が来ても沈まない船か。オリックスの歴史は、平時における財務の重要性を何よりも雄弁に物語っています。
フィルター2:事業の生命線「営業キャッシュフロー」を見よ! 〜伊藤忠商事の非資源戦略〜
配当は、会計上の「利益」からではなく、生々しい「現金(キャッシュ)」から支払われます。本業で現金を稼ぐ力、すなわち営業キャッシュフローこそが、配当の真の原資です。
このお手本が、伊藤忠商事 (8001) です。他の総合商社が資源価格のアップダウンに業績を大きく左右される中、伊藤忠は早くから生活消費関連などの「非資源分野」に注力してきました。
この戦略が、安定した営業キャッシュフローの源泉となっています。資源ブームが来ればライバルに一時的に見劣りすることもありますが、不況期には抜群の強さを発揮する。このブレないキャッシュ創出力こそが、同社の長期にわたる増配記録を支えているのです。
チェックポイント:
- 営業キャッシュフロー: 毎年安定してプラスか?理想は右肩上がりか?
- フリーキャッシュフロー: 設備投資をしてもなお、自由に使える現金は残っているか?
事業モデルそのものが、安定した現金の蛇口になっているか。伊藤忠のビジネスモデルは、その理想形を示しています。
フィルター3:企業の「本気度」を測る配当政策 〜三菱商事が示した”株主との約束”〜
財務が健全で、キャッシュも潤沢。しかし、それを株主に還元する「意志」がなければ意味がありません。その企業の株主還元への「本気度」を見極める上で、従来の「配当性向」だけに注目するのは危険です。そこで重要になるのが「DOE(株主資本配当率)」という指標です。
「配当性向」と「DOE」、何が違うのか?
この二つの指標の決定的な違いは、配当金を計算する際の「分母」にあります。
- 配当性向 (%) = 配当金総額 ÷ 当期純利益 × 100
- DOE (%) = 配当金総額 ÷ 自己資本 × 100
配当性向が参照する「純利益」は、景気の波や一時的な損失などによって、年ごとに大きく変動します。もし企業が「配当性向40%」だけを約束していた場合、利益が半減すれば、配当金も半減してしまいます。つまり、安定性を約束するものではありません。
一方でDOEが参照する「自己資本」は、企業が長年積み上げてきた利益の塊(純資産)です。一時的な赤字を出さない限り、大きく変動することはありません。非常に安定した土台と言えます。
この安定した自己資本を基準に「DOE 3%以上を維持します」と宣言することは、「短期的な利益がどう変動しようと、株主の皆様からお預かりしている資本を元に、安定した配当を出し続けます」という、経営陣からの極めて強い意志表示なのです。これこそが、企業の「本気度」を測るリトマス試験紙となります。
三菱商事が示した”株主との約束”
このDOEを効果的に活用し、市場の信頼を勝ち取ったのが三菱商事 (8058)です。資源価格の変動で利益が揺らぎやすい同社が、「累進配当」に加えて中期経営計画で「DOE」を目標に掲げたのは、「利益のブレを乗り越えて株主還元を続ける」という決意の表れでした。この宣言以降、同社の株価は安定感を増し、多くの長期投資家を惹きつけています。
チェックポイント:
- 配当性向: 高すぎないか?(80%超は危険水域)
- DOEの採用: 経営計画でDOEに言及しているか?
企業は株主とどんな約束を交わしているのか。特にDOEへの言及は、投資家が最も信頼できるコミットメントの形の一つです。
【結論】3つのフィルターが証明するKDDIの「ほったらかし力」
さて、これら3つのフィルターを通して、改めて一つの企業を深掘りしてみましょう。高配当株の王道、KDDI (9433) です。
- 財務の要塞度: 携帯電話事業という巨大なインフラを抱えながら、自己資本比率は40%超を維持。格付機関からも高い評価を得る、まさに鉄壁の財務です。
- 営業キャッシュフロー: 通信料という、景気に左右されにくいストック型のビジネスモデル。毎月、全国民からチャリンチャリンと現金が入ってくる構造は、キャッシュフローの安定性において他の追随を許しません。
- 株主還元の本気度: 20期以上の連続増配という実績が、その意志を何よりも証明しています。さらに「配当性向40%超」という明確な方針を掲げており、ブレがありません。
なぜKDDIが多くの長期投資家に「安心して持てる」と言われるのか。それは、これら3つのフィルターを極めて高いレベルでクリアしているからです。目先の利回りがどうであれ、その裏側にある企業の構造そのものが、長期的な株主還元に適しているのです。
最終チェック:それでも残るリスクと、未来への展望
ここまで3つのフィルターを通して減配リスクを極力排除する方法を解説してきましたが、忘れてはならないことがあります。それは、100%安全な投資は存在しないということです。
例えば、今回ご紹介したフィルターをすべてクリアしている優良企業でも、経営者が突然交代し、新しいCEOが「株主還元より、大規模なM&A(企業買収)を優先する」と宣言すれば、配当方針は一瞬で変わってしまう可能性があります。こればかりは、財務諸表をどれだけ読み込んでも予測が難しい「経営リスク」です。
しかし、それでも私は、日本の高配当株投資には明るい未来が待っていると信じています。これまで多くの日本企業は、株主還元に保守的で、現金を内部に溜め込みがちでした。しかし今、東京証券取引所からの要請もあり、企業は「資本効率」を意識した経営へと大きく舵を切っています。
株主をより重視するこの大きな流れは、私たち配当投資家にとって強力な追い風です。個別のリスクに目を配りつつも、正しい知識で銘柄を選び抜けば、その恩恵を長期にわたって受け取れる可能性は非常に高いと考えています。
まとめ:あなたの銘柄は大丈夫?明日からできる「脱・バリュートラップ」診断
JTの失敗、日産の転落、そしてオリックス、伊藤忠、三菱商事、KDDIの強さ。これらの物語から学ぶべき教訓は明らかです。
高配当株投資は、宝探しゲームではありません。企業の財務諸表や経営方針という「地図」を読み解き、罠を避けながら、本物の宝(=持続可能なキャッシュを生む事業)にたどり着く、知的な冒険です。
今日から、あなたのポートフォリオの銘柄を、この3つのフィルターで診断してみてください。
- 嵐に耐えられる船か?(自己資本比率、D/Eレシオ)
- 蛇口から現金は出続けているか?(営業キャッシュフロー、フリーキャッシュフロー)
- 株主との「約束」はあるか?(配当政策、DOE)
この問いに自信を持って「YES」と答えられる銘柄でポートフォリオを固めていくこと。それこそが、目先の利回りに一喜一憂せず、心穏やかに配当金という果実を受け取り続けるための、唯一無二の戦略なのです。
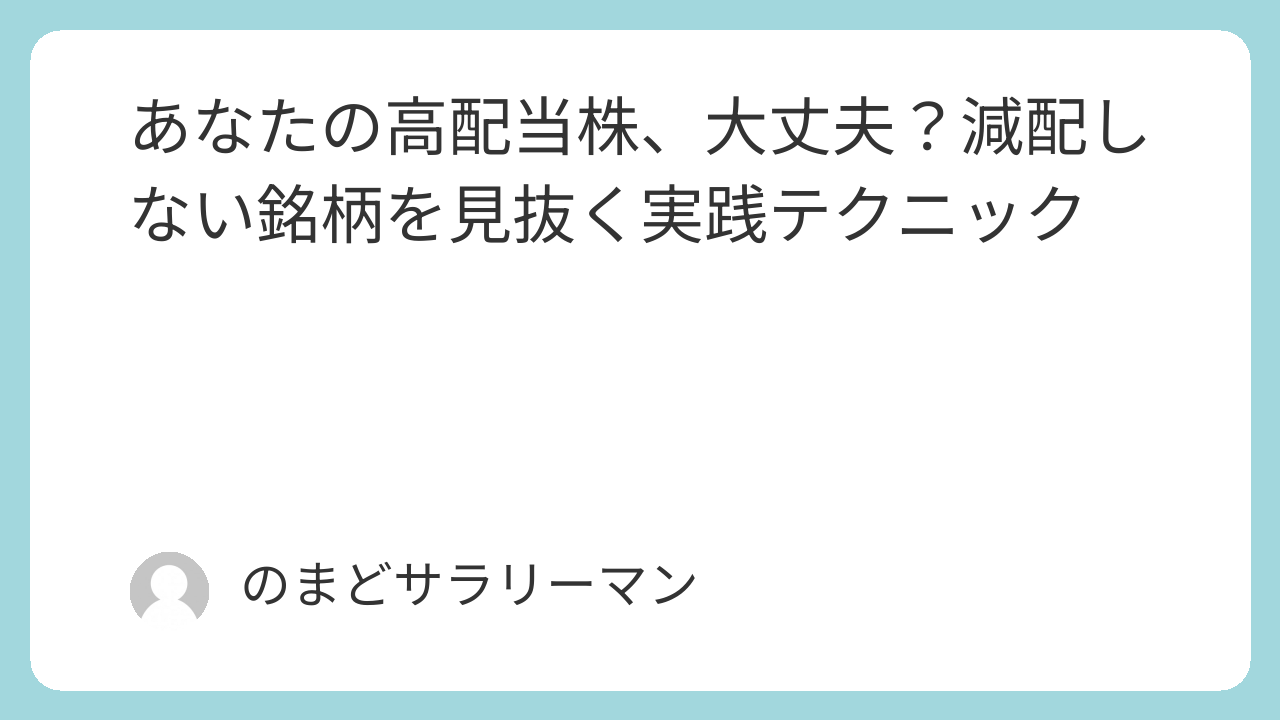
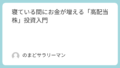
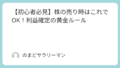
コメント