あなたの職場にもいませんか?
- 指示があるまで、微動だにしない。
- 昔の武勇伝は語るが、今の仕事は語らない。
- 定時になると、誰よりも速く姿を消す。
いわゆる「働かないおじさん」。
彼らの仕事のしわ寄せがあなたに回り、理不尽な思いをしたり、チームの空気が悪くなることに、うんざりしているかもしれません。
「なぜあの人は何もしないのに、自分と同じ(もしくはそれ以上)の給料をもらっているんだ…」
その気持ち、痛いほどわかります。
なぜなら、何を隠そう僕自身が「働かないおじさん」だと思われているであろう張本人だからです。(直接言われたわけではありませんが…かなり自覚しています)
しかし、僕がそうなったのには、単に「やる気がなくなった」からではない、極めて合理的な理由がありました。
この記事では僕自身の経験も踏まえながら、彼らへのストレスを激減させ、あなたの貴重な時間を守るためのトリセツを共有します。
もしあなたが今、彼らの存在に悩んでいるなら、この記事を読めば、明日からの景色が少し変わるはずです。
あなたの職場にもいませんか?「働かないおじさん」あるある事例
本題に入る前に、まずは敵(?)を知るところから始めましょう。おそらく、あなたの頭に浮かんでいるのは、次のようなタイプではないでしょうか。
指示があるまで一切動かない「指示待ち地蔵」タイプ
手持ちの仕事が終わっても、自分から次の仕事を探しに行かない。ただ静かにPCの前で時が過ぎるのを待っている姿は、まさに「地蔵」のよう。悪気はないのかもしれませんが、周囲の忙しさを考えると、ついイラっとしてしまいますよね。
「俺たちの若い頃は…」過去の武勇伝ばかり語る「思い出横丁」タイプ
何かにつけて始まる「昔はこうだった」という武勇伝。そのエネルギーを今の仕事に使ってほしい、というのが本音。変化を嫌い、新しいやり方を受け入れようとしないため、業務改善のボトルネックになることも。
何をしているか不明。でも定時にはきっちり帰る「社内妖精」タイプ
一日中PCに向かっているものの、その画面で何が開かれているのかは謎。忙しい素振りは見せるものの、具体的な成果物は一向に出てこない。まるで会社に住み着く「妖精」のように、その存在は認識できても、実態は誰も知りません。
ため息と愚痴でチームの士気を下げる「空気クラッシャー」タイプ
「どうせやっても無駄」「また面倒な仕事を…」といったネガティブな発言や大きいため息で、チーム全体のモチベーションを奪っていくタイプ。彼らの存在そのものが、職場の生産性を下げていると言っても過言ではありません。
いかがでしょうか。「うちの部署の〇〇さん、全部当てはまる…」と思った方も多いかもしれませんね。
では、なぜ彼らはそうなってしまったのか。僕自身の経験を少しお話しさせてください。
【筆者の告白】私が「頑張るのをやめた」6つの理由
誤解を恐れずに言えば、僕は自らの意思で「会社のために頑張るのをやめた」人間です。かつては出世欲もあり、それなりに働いていましたが、ある時から、会社で出世を目指すことに全く魅力を感じなくなりました。
見えてしまった「出世の天井」。最速で昇進しても社長にはなれない現実
20代の頃は、結果さえ出しつづけていれば会社のトップに立てると信じていました。事実、同期の中でも最速で管理職に昇進しました。しかし、40代に差しかかると、現実が見えてきます。「この会社の構造上、いくら結果を出し続けても自分が社長になる可能性は限りなくゼロに近い」と。大きな目標を失った瞬間でした。
努力と報酬のアンバランス。責任だけ増え、給料は上がらない
年収が1,000万円を超えたあたりから、昇進によるコスパの悪さを強く感じるようになりました。管理職として責任やプレッシャーは倍増するのに、給与の上がり幅は年間100万円程度。このリスクとリターンは全く見合っていない、と。
「ハラスメント」という名の地雷原。部下指導で心がすり減った話
加えて最近では、世の中全体が「〇〇ハラスメント撲滅!」という風潮ですよね。もちろんハラスメント自体を肯定するつもりは全くありません。しかし、現場では部下や同僚に過度な気遣いが求められ、まるで地雷原を歩くような感覚です。指示は出さなければならない、でも相手を傷つけてはいけない、しかも結果は求められる…。この状況に、正直なところ嫌気がさしてしまったのです。
「育ててほしい」でも「叱られたくない」。矛盾に満ちた若手教育への達観
さらに追い打ちをかけたのが、若手教育です。会社からは「若手を育てろ」と言われるものの、少しでも厳しいフィードバックをすれば、すぐに「パワハラだ」と上に報告され、なぜかこちらが怒られる。それなら、と「もう誰にも何も教えない」というスタンスに達観しました。すると今度は、当の若手から「この会社では成長の実感がない」「もっと成長できる環境に行きたい」という声が聞こえてくるわけです。「いい加減にしろよ」と。指導されるのは嫌なのに、成長しないのは人のせい。この他責の姿勢に、深く関わるのはやめようと決めました。
※これらは僕個人の価値観や経験です。
「労働所得」より「資本所得」。投資のほうが効率的という“発見”
ここで僕の視点は大きく変わります。「会社のために身を粉にして労働所得を100万円増やす」よりも、「余力を投資の勉強に使い、資本所得(配当金など)を100万円増やす」方が、はるかに効率的で、将来の安定にも繋がる。この事実に気づいてしまったんです。
日本企業の限界?人生を賭けてトップを目指すには「夢」がなさすぎた
最後のダメ押しは、世界との比較でした。仮にこの会社で社長になれたとしても、報酬はせいぜい数億円程度。一方で、米国企業のCEOは平気で数十億円、数百億円の報酬を得ています。人生という限られた時間をフルベットする対象として、日本のサラリーマンの頂点は、あまりに「夢がない」と感じてしまったのです。
もちろん、これは僕個人の価値観です。
しかし、あなたを悩ませる「働かないおじさん」も、口には出さないだけで、似たような“絶望”や“諦め”を抱えているのかもしれません。
なぜ? 彼らが「働かないおじさん」になってしまう構造的な背景
僕のようなケース以外にも、「働かないおじさん」が生まれてしまう背景には、いくつかの構造的な問題があります。
原因1:時代の変化についていけない「スキルの陳腐化」
かつては優秀だった人も、IT化やグローバル化の波に乗り切れず、自分のスキルが通用しなくなってしまったケース。成功体験が邪魔をして、新しいことを学ぶ意欲を失っています。
原因2:頑張っても評価されない「学習性無力感」
何度か新しい挑戦をしたり、業務改善を提案したりしたものの、上司や会社に評価されなかった経験が重なり、「どうせやっても無駄だ」と無気力になってしまった状態です。
原因3:会社に守られてきた「終身雇用マインド」
大きな成果を出さなくても、会社を辞めさせられることはない。この日本の雇用慣行が、「そこそこでいいや」というマインドを生み出す温床になっている側面も否定できません。
明日から実践!当事者が教える「心が動く」関わり方の5ステップ
彼らの背景を理解した上で、では具体的にどう関わっていけばいいのか。働かないおじさんと自覚している僕だからこそわかる「こう言われたら、少し心が動いたかもしれない」という5つのステップをご紹介します。
ステップ1:【マインドセット編】「変えよう」ではなく「理解しよう」から始める
まず大前提として、「他人を変えることはできない」と割り切りましょう。その上で、「なぜこの人は動かないんだろう?」と、少しだけ相手の背景に関心を持ってみてください。このマインドセットが、あなたのストレスを大きく軽減します。
ステップ2:【タスク管理編】役割と期限をセットで「具体的」にお願いする
「これ、お願いします」という曖昧な依頼はNGです。「この資料の〇ページのデータを、△△のフォーマットにまとめて、明日の15時までにいただけますか?」のように、役割・タスク・期限を明確にして依頼しましょう。彼らは「何をすればいいか分からない」状態であることが多いのです。
ステップ3:【コミュニケーション編】「教えてください」スタンスで、眠れる知識を呼び覚ます
彼らは長年の経験で、あなたも知らない知識や社内人脈を持っている可能性があります。「〇〇さん、昔この案件を担当されてましたよね?少し教えていただけませんか?」と、敬意をもって頼ることで、彼らの眠っていたプライドが刺激され、意外な協力が得られることがあります。
ステップ4:【承認欲求編】「さすがですね!」小さな承認が、再起動のきっかけになる
何かをしてもらったら、たとえ小さなことでも「ありがとうございます!さすがですね、助かりました!」と少し大げさに伝えてみてください。彼らは近年、誰かから承認される経験が圧倒的に不足しています。この一言が、彼らの心を動かす再起動スイッチになるかもしれません。
ステップ5:【最終手段編】一人で抱えず、上司を巻き込み「記録」を残す
何を試してもうまくいかない、実害が出ている場合は、一人で抱え込まずに必ず上司に相談しましょう。その際は「〇〇さんが働かなくて困ります」という愚痴ではなく、「△△の業務が、〇〇さんの遅延によりこれだけ滞っています」と事実と記録(メールなど)を元に、客観的に報告するのがポイントです。
それでも変わらない…自分の心とキャリアを守るための思考法
様々な手を尽くしても、残念ながら相手が全く変わらないケースもあります。そんな時は、相手にエネルギーを注ぐのをやめ、自分自身を守ることにフォーカスを切り替えましょう。
「課題の分離」で割り切る。それはあなたの問題ではない
「あの人が働かない」のは、あくまで“あの人の課題”です。あなたがそのことで悩み、パフォーマンスを落とす必要は一切ありません。自分のやるべき仕事に集中し、境界線を引きましょう。
彼らを「反面教師」と捉え、自分のスキルアップに集中する
「自分は10年後、20年後、ああはならないぞ」と強く誓いましょう。彼らの姿は、学びを止め、変化を恐れた人間の末路です。そうならないために、自分はどんなスキルを身につけるべきか? 会社の外でも通用する専門性は何か? を考える絶好の機会と捉えるのです。
社内に「味方」を見つけ、ストレスを共有・分散させる
おそらく、あなたと同じように感じている同僚がいるはずです。信頼できる人と愚痴を言い合ったり、情報交換したりするだけでも、ストレスはかなり軽減されます。一人で溜め込まないことが重要です。
まとめ:あなたの貴重なエネルギーを「おじさん問題」で浪費しないために
今回は、「働かないおじさん」への対処法を、僕自身の経験も交えて解説しました。
最後に、一番伝えたいことがあります。
それは、「あなたの時間は、有限だ」ということです。
「働かないおじさん」にイライラしたり、彼らの仕事のカバーをしたりしている時間は、本来あなたが自分のスキルアップやキャリア形成、そして資産形成に使うべきだった時間です。
彼らを無理に変えようとするのではなく、うまく付き合い、時には反面教師にしながら、あなたはあなたのやるべきことに集中する。そして、会社に依存しなくても生きていける力を着々と身につけていく。
それが、この問題を解決する唯一にして最強の方法だと、僕は信じています。
この記事が、あなたの明日からのアクションのヒントになれば幸いです。
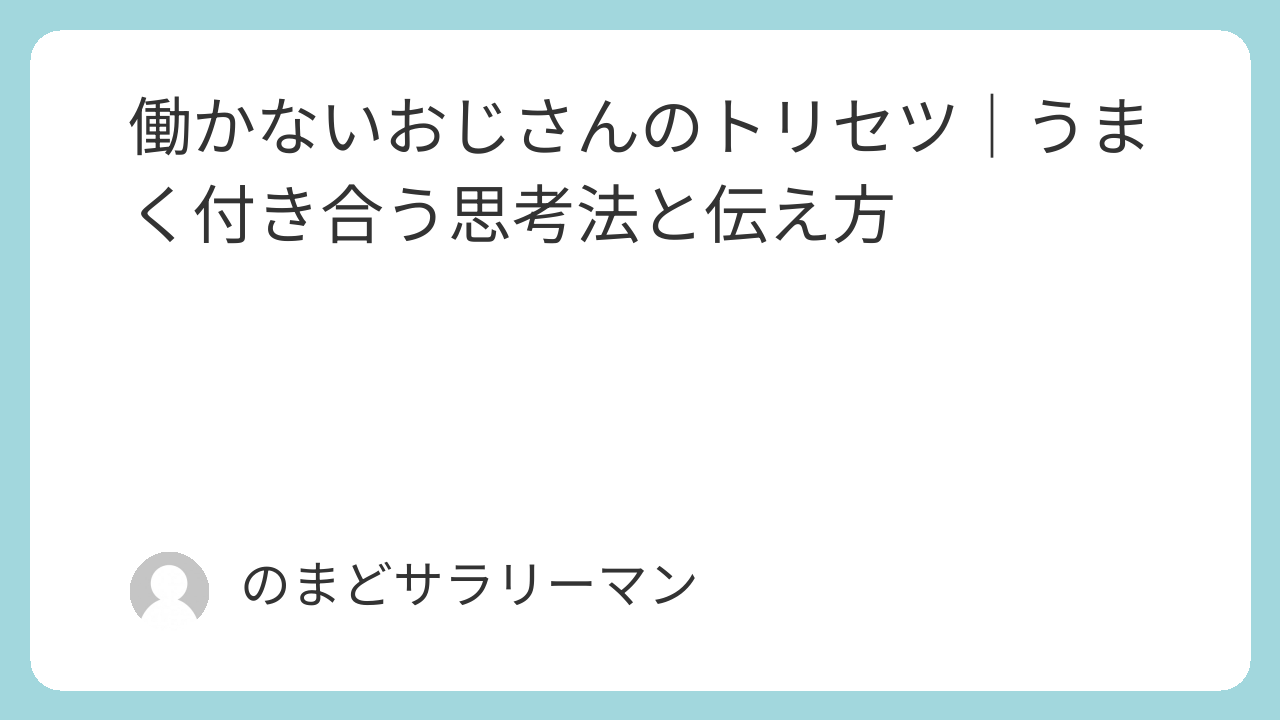

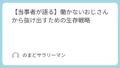
コメント