理系の就職活動や転職で学歴フィルターがあるのは常識。今回は理系の学歴フィルターでボーダーラインにいる大学について解説していきます。特に化学メーカーの就職・転職に当てはめてみてください。また文系に関しては以下の記事にまとめています。
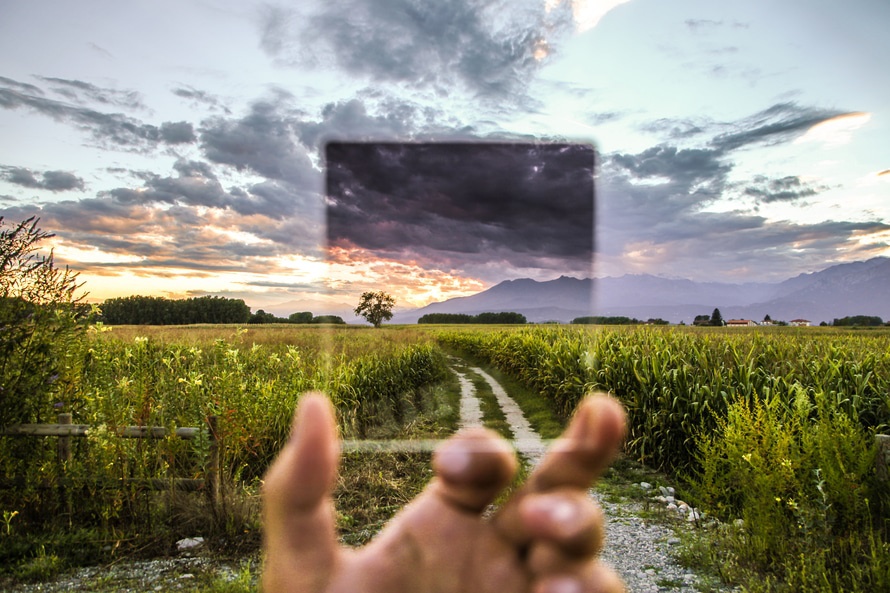
【説明】学歴フィルターとは名前の通り「学歴によって採用するかどうかを判断する基準」のこと。その手法は①リクルーターを派遣しない②会社説明会を「満席」にして参加させない③ESを見ないで落とす、などがあります。
【注意】2chとは一切関係ありません。
【理系】学歴フィルターのボーダーライン大学
理系の場合、文系とは違っていて研究室に入った段階で勝負の9割は決着済み。
ボーダーラインにいる大学では上位研究室に入れないと厳しい就職活動を強いられます。
ただし理系学生はメーカー中心に就職活動するかと思いますが、文系よりも学歴フィルター甘いのでその点についてはご安心ください。
それでは企業ランクごとに見ていきましょう。
就職偏差値60〜の一流企業ボーダー
- 地方国公立大学の上位研究室&成績優秀
- >中位私大の上位研究室&成績優秀(東京理科/MARCH/関関同立/四工大)
- >>>>>>それ以外(ほぼES通過しない)
これらの大学は可能性ゼロではありません。
が、ボーダーラインであるため確率低い。不定期で各校から1~3人、採用される可能性のある大学です。去年は同志社から採用したから今年は信州大かなぁ、といった感度。
でも不定期なので教授推薦もしくは学校推薦があったとしても、魅力のない学生は容赦なく落ちます。
また理系の場合、大学も重要ですが研究室も重要。
上位研究室に所属していれば地方国公立や中堅私大からでも可能性あります。逆に下位クラスのしょうもない研究室に所属の場合、ES通過すらしません。
▼▼▼▼▼▼
以上は一般的な傾向、あとは会社のクセです。
中堅私大が好きな企業、私大よりも国公立が好きな企業。
採用のクセがありますので、あらかじめ採用実績を「就職四季報」でチェックしておきましょう。
就職偏差値56〜59の大企業ボーダー
- 地方国公立大学の上位研究室&成績普通〜ダメ
- >中位私大の上位研究室&成績普通〜ダメ(東京理科/MARCH/関関同立/四工大)
- >>地方国公立その他・中位私大その他
- >>>下位私大(日東駒専以下クラス)の上位研究室&成績優秀
世の中の景気動向に採用人数が大きく左右されるので何とも言えませんが…
2017卒・2018卒はこのイメージで大丈夫でしょう。
就職偏差値55以下の企業
学生を集めるのすら大変な企業。
学歴フィルターは存在しないと見ておいて大丈夫です。
まとめ
地方国公立や中堅私大の学生はどんぐりの背比べ。
中堅私大よりも地方国公立のほうが上だろ!
同志社より関学のほうが上だろ!
信州大より横浜国大が上だろ!
いやいや、そんなことはない!東京理科が一番だ!
とかとか…2chで熱く議論されています…
でも真実は人事採用担当からすると理系の場合、旧帝大・東工大・東京農工・早慶以外の学歴であればどこも同じ。ボーダー付近では大学名よりも所属している研究室が重要。
しょうもないことは考えずシンプルに上記のような学歴フィルターを使います。



コメント
理科大より駅弁のほうがうえとかねえわwwww
理科大は駅弁同様カスなのでどうでもいいけど、なんでボーダーより上に農工大があるのか意味不明。
某大学の電気系学科を卒業したものですが、
研究室のランクとはどういう意味でしょうか?
教授の実績・知名度か、研究内容か、学生の質なのかといったことでしょうか。
ここでは言及されてませんが、個人的には理系は大学の偏差値よりも、
学科(履修科目、学んだこと)、研究室の研究内容(分野)の方が大事だと思っています。
具体的には、機電系>情報系・化学系>バイオ系、といった感じです。
もっと言うと、自動車系の仕事がしたければ、
流体力学や制御工学(できれば自動車工学)を履修(研究)しているかは問われるかと思います。
以上、お忙しいとは存じますが回答いただけると幸いです。
返答が遅くなり誠に申し訳ありません。
ご指摘いただきましたとおり、
理系は研究室で何を学んだか、もっとも就職に影響します。
たとえば化学メーカーだと、化学系の研究室からの採用がほとんどになりますし
自動車業界だと、いただいたような履修が必要となりますね。
この前提を飛ばして話を進めていました・・・。
当記事は、化学系なら化学系のなかで「研究室のランクをみる必要がある」
という内容となっております。
説明が不足しており、申し訳ありません。
また研究室ランクの定義につきまして以下、補足解説いたします。
①企業との共同開発
・共同開発はどの企業とやっているのか?
・共同開発先の企業の格=研究室の格
②研究室のOB/OG
・OB/OGがどんな企業に就職しているのか?
・大学のレベルよりも格上の企業=研究室が優れている
③教授の人脈
・民間企業出身者 > 大学プロパー
④教授および研究室の実績
・その研究分野における教授の「業界内での権威」
・実績のある教授 >>> 実績を持たない教授
ざっくりとは、
このようなポイントで研究室のランクをみてけば良いかと存じます。
学生からの人気研究室が必ずしもトップクラスとは限りません。
長文となり大変失礼いたしました。
ご参考になりましたら幸いです。
管理人
学歴ロンダリングについてはどう影響しますか?
理系は修士課程で民間就職する方が多いですが、早慶理科大や地方国立大から東大院に行く人など、世の中に数多存在します。
やはり最終学歴が最も重要ですか?それとも学部の名前も見られるのでしょうか?
東京農工ww
地方国立理系大学生の者です。大企業に行くためには上位研究室に入るべきだと書かれていますがこれは本当なんでしょうか?
私の所属する大学は神戸筑波のワンランク下辺りのレベルですが毎年先輩方がトヨタをはじめ多くの名だたる企業の内定を勝ち取っています。就活体験記などを見ると色んな研究室からそういった人を輩出しておりとても研究室によって就活に差があるとは思えません。毎年人気、不人気の研究室は存在しますが、理由としては概ね皆の興味ある分野が似通っている(例えば工学部であればロボット関連は人気)、朝から晩まで拘束されるような所謂ブラック研究室は避けられる、等であって、そういった不人気研究室からも大手に内ている人はいます。なので研究室は関係無く、大学自体のレベルや、成績や学会発表など本人の実績にのみ依存しているように感じます。
お忙しいこととは存じますが回答していただけると嬉しいです。
ててさんと同様の意見です。大企業への就職において研究室が合否を左右するとは思えません。
大抵は学科推薦で就職が決まっているように見えますし、学科推薦は成績と院試の点数で優先順位が決まるため研究室の差はありません。また、人事の方々はそこまで細かく研究室ごとの特徴を理解しているんでしょうか?
私は三大都市圏の旧帝国大に通う学部新3回生です。就職については新M2の先輩から聞いただけで自分が詳しく調べたわけではないですがそこまで外れてないと思います。
左右するとは言わないまでも研究室によってはいわるゆコネがあり贔屓される
具体的に言えばリクルーターの派遣や見学の誘い、食事会など
研究内容が事業あるいは現在力を入れてる基礎研究に直接関係するほどそれは顕著